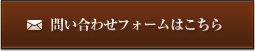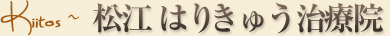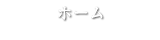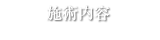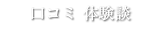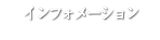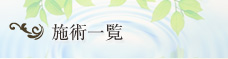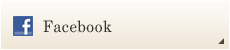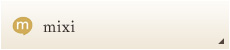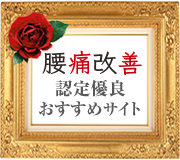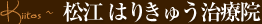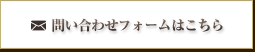カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年6月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (19)
- 2023年3月 (8)
- 2023年1月 (3)
- 2022年6月 (1)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (1)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (3)
- 2015年11月 (2)
- 2015年10月 (2)
- 2015年9月 (2)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (3)
- 2015年6月 (2)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (13)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (9)
- 2014年9月 (4)
- 2014年8月 (13)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (3)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (4)
- 2014年3月 (11)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (7)
- 2013年12月 (16)
- 2013年11月 (8)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (13)
- 2013年6月 (14)
- 2013年5月 (24)
- 2013年4月 (37)
最近のエントリー
- ・鍼灸(はりきゅう)
- ・その他の手技による治療
- ・整体 カイロプラクティック オステオパシー など
- ・アスレチックリハビリテーション
- ・アロマオイルセラピー アロマオイルトリートメント
- ・リンパドレナージュ
- ・タクティールケア/タッチセラピー
- ・炭酸ミスト
- ・物理療法
- ・トレーニング指導/アドバイス
- ・ダイエット指導/アドバイス
- ・気になる料金。。。
HOME > インフォメーション > アーカイブ > 健康・医療情報の最近のブログ記事
インフォメーション 健康・医療情報の最近のブログ記事
高齢者における「フレイルドミノ」をご存知ですか?
高齢者のフレイルは、身体的、認知的、社会的な機能の低下が進行し、
以下に、高齢者のフレイルがもたらす危険性をいくつか説明します。
フレイルの高齢者は、筋力低下やバランスの悪化が起こりやすいため、転倒や骨折のリスクが増加します。
転倒は高齢者にとって重大な健康リスクであり、骨折や内出血、その他の合併症を引き起こす可能性があります。
フレイルの進行によって認知機能が低下することがあり、認知症の発症リスクが高まる可能性があります。
認知症は日常生活に大きな影響を与え、本人および家族に負担をかけることがあります。
フレイルの高齢者は、食欲不振や栄養摂取の低下が見られることがあります。
栄養不足は免疫力の低下や体力の減退を招き、病気に対する耐性が低下する可能性があります。
フレイルの進行により、高齢者の日常生活動作(ADL)への自己介助が必要になることがあります。
これにより、本人の生活の質が低下するだけでなく、家族や介護者の負担も増える可能性があります。
フレイルの高齢者は、外出や社会的な交流が難しくなることがあります。
これにより、孤独感やうつ病のリスクが高まることがあります。
(松江はりきゅう治療院)
2023年8月 3日 17:32





関節の痛み:関節リウマチによる指の変形と、ヘバーデン結節による指の変形は別物です
(松江はりきゅう治療院)
2023年5月11日 12:17





筋繊維痛症のガイドラインと鍼治療の研究論文の紹介
副作用や相互作用にも注意する必要があります。
補完的・代替療法も考慮される場合があります。
信頼性のある施術者によって行われるべきです。
教育と自己ケア:
個別の症状に合わせた治療:
筋繊維痛症の治療については、患者の症状や状態に合わせて総合的なアプローチが推奨されています。
最新のガイドラインや専門医の指導を参照し、適切な治療を受けるようにしましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Treatment of fibromyalgia with acupuncture: a randomized controlled trial.
Mayo Clin Proc. 2006;81(6):749-757. doi:10.4065/81.6.749
この研究では、鍼治療が筋繊維痛症の症状を改善する可能性があることが示されました。
研究参加者は、鍼治療を受けた群とシャム鍼治療を受けた群にランダムに割り付けられ、
治療前と治療後に痛みや身体機能、心理的な側面などを評価されました。
鍼治療を受けた群では、痛みの強度や身体機能の改善が見られ、心理的な側面でも治療効果があったとされています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Martin-Sanchez E, Torralba E, Diaz-Dominguez E, Barriga A, Martin JL.
Effectiveness of acupuncture for fibromyalgia treatment: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
J Acupunct Meridian Stud. 2019;12(4):109-122. doi:10.1016/j.jams.2019.02.001
この研究では、ランダム化比較試験のメタ分析により、
鍼治療が筋繊維痛症の症状を改善することが示されました。
研究には、鍼治療を受けた群と対照群の総計11件のランダム化比較試験が含まれ、
痛みの強度や身体機能の改善が見られたとされています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Acupuncture for fibromyalgia: an overview of systematic reviews.
Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:615063. doi:10.1155/2015/615063
この研究では、過去に行われた鍼治療に関するシステマティックレビューを概観し、
鍼治療が筋繊維痛症の症状を改善することが示されていることが報告されています。
ただし、治療の長期的な効果に関する研究が不足していることが指摘されています。
Acupuncture for pain management in patients with fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
J Rheumatol. 2010;37(11):2256-2266. doi:10.3899/jrheum.100104
この研究では、鍼治療が筋繊維痛症の痛み、睡眠障害、うつ病の症状を改善することが示されました。
研究には、鍼治療を受けた群と対照群の総計8件のランダム化比較試験が含まれ、
鍼治療を受けた群では、痛みの強度が軽減され、睡眠障害やうつ病の症状も改善したとされています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial.
Acupunct Med. 2016;34(4):257-266. doi:10.1136/acupmed-2015-010950
この研究では、鍼治療が筋繊維痛症の痛みや身体機能の改善に有効であることが示されました。
研究には、鍼治療を受けた群とシャム鍼治療を受けた群の総計153人が参加し、
鍼治療を受けた群では、痛みの強度が軽減され、身体機能の改善も見られたとされています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Acupuncture for osteoarthritis of the knee: a systematic review.
Arthritis Rheum.2001;44(4):819-825. doi:10.1002/1529-0131(200104)44:4<819::aid-anr138>3.0.co;2-p
この研究に参加した患者は、筋繊維痛症の診断を受けたわけではありません。
しかし、この研究結果は、筋繊維痛症における鍼治療の可能性を示唆しています。
これらの研究結果から、
しかし、いずれの研究も治療効果や安全性についての一定の結論を出すには十分な証拠がないとも報告されています。
より多くの高品質な研究が必要であり、鍼治療の筋繊維痛症に対する効果を明確にするためには、
さらなる研究が必要とされています。
また、鍼治療は個人差があり、効果がある場合でも一定の期間を経て効果が現れることがあるため、
(松江はりきゅう治療院)
2023年4月27日 08:08





足がつる。その原因と対策・治療方法。鍼は効く?
 原因はいくつか考えられますが、代表的なものには以下のようなものがあります。
原因はいくつか考えられますが、代表的なものには以下のようなものがあります。→良質な水とミネラルの摂取をしてください
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 を過剰に摂取すると、体内の水分やミネラルが失われることがあります。
を過剰に摂取すると、体内の水分やミネラルが失われることがあります。そのため、足がつることがあります。
→アルコールはほどほどに。。。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
交感神経が優位になり、筋肉が硬直し足がつることがあります。
→副交感神経が優位になれるようにお手伝いします
【血行不良】
血行不良の原因には、運動不足、肥満、加齢、冷え性、喫煙、高血圧、糖尿病などが挙げられます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
筋肉が硬くなり、血液循環が悪くなることがあります。このため、足がつることがあります。
→筋肉がほぐれるような、さまざまなメニューを提供できます
そのため、足がつることがあります。
→初期の糖尿病は低周波鍼通電療法が功を奏します。
本態性の高血圧は鍼がお役に立てます。
リウマチによる関節の痛みは筋肉をほぐすことでかなり楽になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
脊髄を取り巻く骨の空洞(脊柱管)が狭くなってしまう症状のことです。
腰椎管狭窄症が進行すると、脊髄に圧迫がかかり、足に痛みやしびれ、痺れ、つるなどの症状が現れることがあります。
椎間板と呼ばれる腰椎の間にあるクッションの部分が、
繊維輪を破って内部から飛び出した状態のことです。
この状態になると、神経根や脊髄が圧迫され、足に痛みやしびれ、痺れ、つるなどの症状が現れることがあります。
→ 低周波鍼通電療法や通常の鍼治療、マッケンジー療法で対処します
例えば、利尿剤や抗うつ剤などが該当します。
→薬剤師さんに相談してください
筋肉の収縮と弛緩がうまくいかなくなり足がつることがあります。
代謝が悪くなり、体温が下がりやすくなります。
(松江はりきゅう治療院)
2023年4月18日 08:59





副腎疲労について
長期間にわたるストレスや疲労によって、副腎皮質ホルモンの分泌が低下し、
身体的・精神的な疲労や不調が起こる状態のことを指します。
副腎皮質ホルモンは、
ストレスに対する対応や免疫系の調節、血糖値の調整などに重要な役割を果たしています。
疲れやだるさ、睡眠障害、ストレス耐性の低下、集中力や記憶力の低下、
不安やうつ症状、消化器系の不調、体重増加や減少などがあります。
これらの症状は、他の疾患でも見られることがありますが、
副腎疲労の場合は、症状が長期間続くことが特徴的です。
ストレス、不規則な生活習慣、栄養不良、感染症、
アレルギー、腸内環境の乱れなどが挙げられます。
ストレスを減らすためのライフスタイル改善、栄養バランスの改善、
適度な運動、睡眠の改善、サプリメントの使用などがあります。
ただし、副腎疲労という疾患自体が医学的に確立されているわけではないため、
(松江はりきゅう治療院)
2023年4月 9日 14:43





首・腰の牽引治療のエビデンス
少なくないと思います。
首や腰の牽引治療は、
慢性的な首や腰の痛み、神経根症状、
頸部・腰椎の椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの治療に広く用いられています。
椎間板の間を広げる
椎間関節に掛かる負担を軽減する
椎間孔を広げる
脊椎周辺の筋肉のストレッチをする
などと説明を受けていることでしょう。
牽引する強さを決めるのは、ぶっちゃけテキトーです。
「この人ならこの程度の力で引っ張ってみるか」とアバウトに決めます。
その結果、牽引し終わった後、痛みが増したり、
何をされたんだかよくわからなかった、というような結果になることもあります。
首や腰を固定するのにも、意外とコツが必要です。
首の牽引に至っては、座る位置とか、引っ張る角度が微妙に異なる場合があります。
そのようなことをクリアしても、実際に行うのは10分だけとか。。。
まあ、そんなぶっちゃけ裏話もいいのですが、
牽引治療に関するエビデンスとなると、不確実性が残されています。
一方で、効果は一時的であり、長期的な治療効果については不明確です。
また、治療前にどの患者がこの治療に反応するかを正確に予測することは困難です。
ただし、腰椎椎間板ヘルニアの患者には、牽引治療が有効である可能性があるとの研究結果もあります。
個々の患者に応じた治療法の選択が重要です。
治療前に、症状や病歴、身体検査などを総合的に評価することが必要です。
------------------------------------------------------------------------
Kuijper et al. (2004).
A systematic review on the effectiveness of cervical traction.
Physiotherapy Canada, 56(4), 205-212.
この論文は、首の牽引治療の効果についてのシステマティックレビューです。
著者らは、ランダム化比較試験を含む、15の研究を分析しました。
その結果、牽引治療は、一部の患者において痛みの軽減や機能改善に効果があることが示されました。
ただし、長期的な治療効果については不明確であり、
治療前にどの患者がこの治療に反応するかを正確に予測することは困難と結論づけられました。
------------------------------------------------------------------------
Clarke et al. (2005).
A systematic review of manual therapies for the thoracic spine: a critical appraisal of literature.
Physiotherapy, 91(4), 156-175.
この論文は、胸椎の牽引治療を含む、手技療法の効果についてのシステマティックレビューです。
著者らは、ランダム化比較試験を含む、13の研究を分析しました。
その結果、牽引治療は、短期的な効果があるものの、長期的な治療効果については不明確であり、
臨床的な適用範囲が限られていることが示されました。
The effectiveness of traction for back pain: a systematic review and meta-analysis.
Clinical Rehabilitation, 30(11), 1079-1089.
この論文は、腰の牽引治療に関するシステマティックレビューおよびメタアナリシスです。
著者らは、ランダム化比較試験を含む、10の研究を分析しました。
その結果、牽引治療は、一部の患者において短期的な痛みの軽減に効果があることが示されました。
ただし、長期的な治療効果については不明確であり、
治療前にどの患者がこの治療に反応するかを正確に予測することは困難であると結論づけられました。
------------------------------------------------------------------------
(松江はりきゅう治療院)
2023年4月 7日 18:37





慢性疲労症候群(Chronic Fatigue Syndrome、CFS)とは
この症候群は、
睡眠不足、筋肉の痛み、関節痛、頭痛、集中力の欠如、
喉の痛み、リンパ節の腫れ、悪心、食欲不振、体温の変化などの他の身体的な症状と共に現れます。
一般的には6ヶ月以上にわたって持続する疲労感を示します。
CFSは、現在までに特定の原因が見つかっていないため、完全には解明されていませんが、
免疫系や神経系、ホルモンバランスの異常、
ウイルス感染、ストレスなどが関連していると考えられています。
年齢層は10代から40代にかけての人々が最も影響を受けやすいとされています。
行動療法、認知療法、リラクゼーション法、運動療法などがあります。
複数箇所の筋肉がパンパンに張っている場合、
当院でも対処可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
(松江はりきゅう治療院)
2023年4月 6日 12:25





顎関節症の原因となる筋肉を緩めましょう
症状は、
顎の痛みや音がする、
口を開け閉めするときに違和感がある、
咬み合わせが合わなくなる、
などがあります。
顎関節症の原因となる筋肉は、以下です。
咬筋:咀嚼に関わる筋肉で、過度な力がかかることで顎関節症を引き起こすことがあります。
これらの筋肉が緊張し、硬くなることで、
顎関節に負担がかかり、症状を引き起こすことがあります。
顎関節症の治療には、筋肉の緊張を緩和することが大切であり、
口の開け閉め運動やマッサージ、理学療法、ストレス管理などが効果的です。
内側翼突筋が硬くなると、顎を引っ張り続けるために
顎関節に負担がかかり、顎関節が痛くなることがあります。
また、内側翼突筋が硬くなることで、顎の咬み合わせの調整が上手くいかなくなり、
顎関節症の症状が悪化することがあります。
一般的には内側翼突筋を緩めるにはマッサージしたり、低周波鍼通電療法(筋パルス)を行ったり
オステオパシーのストレイン・カウンターストレインというテクニックなどを用いたりするのですが、
炭酸水や強い磁力の磁石を使用することで内側翼突筋を緩めることも可能です。
詳細はここでは記載しません。
来院されたときにお伝えします。
(松江はりきゅう治療院)
2023年4月 6日 09:11





握力の低下は認知機能の低下・認知症と関係します
引き起こされることがあります。これらの要因は、認知症のリスク要因としても知られています。
これらの方法は、認知機能の改善や認知症の発症リスクの低下にも効果的であることが示唆されています。
定期的な運動やバランスの取れた食事、ストレスの管理などを含めた
健康的なライフスタイルの維持が重要です。
また、定期的な健康チェックや認知機能の評価を受けることも推奨されます。
握力と認知機能の間には密接な関係があることが示されています。
一部の研究によると、握力が強い人は、認知機能が高い傾向にあるとされています。
また、握力が強い人は、認知症のリスクが低い可能性があるという研究結果もあります。
一部の研究によると、握力の低下は認知症の初期症状の1つであり、
進行した認知症の患者では握力が非常に低下していることが示されています。
一方、握力の低下は認知症の発症を予測する指標としても有用かもしれません。
握力を改善することは、認知機能の維持や認知症のリスク低下に役立つ可能性があります。
そのため、健康的なライフスタイルの維持に加え、
定期的な運動や筋力トレーニングなどの方法を取り入れることが重要です。
以下にその研究論文の一例を挙げます。
------------------------------------------------------------------
(2017年、Journal of Alzheimer's Disease)
最初の調査時に、参加者の握力と認知機能が測定され、2年後に再度測定が行われました。
具体的には、握力が1kg低下するごとに、認知機能テストのスコアが0.03点低下することが判明しました。
また、握力の低下が認知機能の低下を予測する有効な指標となる可能性があることが示されました。
高齢者を対象に実証的に示した先駆的な研究として注目されています。
・"Association between handgrip strength and cognitive impairment in elderly people: a systematic review"
(2020年、Aging Clinical and Experimental Research)
:この研究では、高齢者を対象に、握力の低下と認知機能の低下との間に関連性があることが示されています。
体系的にレビューし、結果をまとめたものです。
これらの先行研究では、総計14,955人の高齢者が調査され、
握力と認知機能の関連性が評価されていました。
レビューの結果、握力の低下が認知機能の低下と関連していることが示されました。
特に、握力が弱い高齢者は、記憶力、認知速度、注意力、実行機能などの
多くの認知機能の面で低下していることが報告されました。
その関係性の重要性が再強調されました。
また、高齢者の健康維持や認知機能の改善において、
握力の改善が有効なアプローチの一つであることが示唆されました。
・"Grip strength is associated with cognitive performance in Schizophrenia and the general population: a UK Biobank study of 476559 participants"(2021年、Translational Psychiatry)
:この研究では、健常者と統合失調症患者を含む大規模な人口調査を行い、
握力と認知機能の間に関連性があることが示されています。
握力と認知パフォーマンスとの関連性を調査しました。
握力と認知パフォーマンスのデータを収集しました。
その結果、握力が高い人ほど、認知パフォーマンスが良かったことが示されました。
具体的には、握力が強い人は、記憶力、処理速度、反応時間、認知機能総合得点など、
多くの認知パフォーマンス指標で高得点を示しました。
つまり、統合失調症患者でも、握力が高い人ほど認知パフォーマンスが良かったということです。
統合失調症患者を含む一般人口においても、関連性があることを示唆しています。
また、握力の強化が認知機能の改善につながる可能性があることを示唆しています。
------------------------------------------------------------------
しかし、この分野の研究はまだ進んでいる段階であり、
今後の研究によって、さらに詳細な関連性が明らかになることが期待されています。
(松江はりきゅう治療院)
2023年4月 5日 09:40





スーパーなどにある「逆浸透膜」を利用した浄水器について
「逆浸透膜」を利用した浄水器(利用無料)が設置されているので
便利でおいしいため、よく使っていたのですが、欠点もわかってきました。
逆浸透膜を利用した浄水器は、
その特性から飲料水や医薬品、電子部品の製造などの産業分野でも利用されています。
高品質な水を提供することができます。
細菌やウイルス、微小な有機化合物、塩分、金属イオンなどを除去することができます。
環境に優しく、安全性が高いとされています。
(ただし、一部の逆浸透膜浄水器には、ミネラルを補充するフィルターが搭載されている場合もあるようですが。)
水を清潔にするために設計されており、ミネラルも取り除く可能性があるため、
ミネラルの補充が必要な場合があるということです。
そのため、
逆浸透膜浄水器で除去されたミネラルや微量栄養素は、食品やサプリメントから補う必要があります。
初期コストやランニングコストがかかることが欠点とされています。
設置してる店では、どの程度の頻度でメンテナンスされているのかも気になりますね。
(松江はりきゅう治療院)
2023年4月 4日 08:52